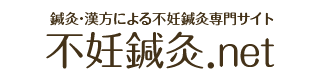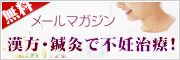【男性不妊】でよく使われる漢方薬ってどんな薬?5(柴胡加竜骨牡蛎湯1)(20160609)
2016-06-10 [記事URL]
こんにちは!
馬場聖鍼堂 男性不妊担当の万木祥太郎です。
じめじめと暑い季節になってきましたね。
熱中症対策は大丈夫でしょうか?
とはいえ妊活中は冷房で身体を冷やしたくないですし
難しい季節ですよね。
また妊活中の男性にとっては股間の熱対策がとても大事な季節でもあります。
ボクサーパンツやブリーフ派の方や自転車通勤をされている方などは
特に気を付けて下さいね!
ということで今回も僕のメルマガは
男性不妊でよく使われる漢方薬を東洋医学的に解説するシリーズです。
今まで紹介してきた漢方薬は【補中益気湯】と【八味地黄丸】でした。
5回目の今回は
3つ目の漢方薬として【柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)】を
東洋医学的に解説してみようと思います。
過去の解説について知りたい方ははメルマガバックナンバーをご覧下さいね。
【補中益気湯】
http://www.funinchiryou.net/20151225-2/
http://www.funinchiryou.net/20160205-2/
【八味地黄丸】
http://www.funinchiryou.net/20160318-2/
http://www.funinchiryou.net/20160429-2/
では、【柴胡加竜骨牡蛎湯】を見ていきましょう。
例によってT社の説明書きから見てみます。
効能、効果としては
比較的体力があり、心悸亢進、不眠、いらだち等の精神症状があるものの次の諸症
高血圧症、動脈硬化症、慢性腎臓病、神経衰弱症、神経性心悸亢進症、てんかん、ヒステリー、小児夜啼症、陰萎
とあります。
一見、男性不妊と関係のありそうなのは
陰萎くらいに見えますね。
陰萎は、いわゆる勃起不全や勃起障害のことです。
前回までにご紹介した補中益気湯や八味地黄丸の効能にもありました。
だからといって、
勃起不全や勃起障害が男性不妊の主な原因であったとしても
補中益気湯や八味地黄丸、柴胡加竜骨牡蛎湯の3つの漢方薬のどれを飲んでもOK
というわけではありません。
では、柴胡加竜骨牡蛎湯はどういう場合が適しているのでしょうか。
東洋医学の古典から考えてみたいと思います。
柴胡加竜骨牡蛎湯は『傷寒論』という東洋医学の古典に書かれています。
その本の中で柴胡加竜骨牡蛎湯はこのように紹介されています。
“傷寒八九日、之を下し、胸満煩驚、小便不利、譫語、一身尽く重く、転倒すべからざるものは、柴胡加竜骨牡蛎湯を主る”
つまりどういうことか今の言葉で平たく説明すると
熱性で急性の風邪を引いてから、便を下したのち、
胸やみぞおちのあたりが苦しくなったり動悸がしたり
尿が出にくくなったり、うわごとを言ったり、
身体が重くて自分自身で寝返りを打つこともできなくなってしまった人には
柴胡加竜骨牡蛎湯が効きます
ということです。
まだどうにも男性不妊と結びつきませんね。
ポイントは、胸が苦しかったり動悸がしたり・・・
という部分だと思います。
(その他の部分も大事なのですが、わかりやすいところで説明します)
どういう状況が思い浮かびますでしょうか?
日常生活に置き換えてみると
過度なストレスや心配事などにより胸やみぞおちが苦しくなっている状況です。
以前のメルマガで陰萎の原因の一つにストレスがある
ということをお伝えさせていただきました。
(バックナンバーはこちらです→http://www.funinchiryou.net/20141031-2/)
慢性的なストレスは腎精を消耗し生殖能力を弱めてしまいますし
ストレスや心配事などから心臓に弱りがでてしまうと
心血の不足などに陥り、陰萎につながることがあるのです。
(ここでいう腎臓や心臓は東洋医学的な考え方ですので
実際に腎臓や心臓に現代医学的な病気があるというわけではありません)
つまり、
いわゆるストレスが原因で勃起障害や勃起不全という陰萎の症状が出ている場合に
柴胡加竜骨牡蛎湯が効果的だということですね。
慢性的にストレスを感じることが多かったり
みぞおちのあたりにいつも違和感があったり
という方にはあっている漢方薬かもしれません。
実際、クリニックで柴胡加竜骨牡蛎湯を処方してもらっているゲストのお話を伺うと
慢性的なストレスを感じていたり、タイミングED等で悩まれている方が
多いように感じます。
ではなぜ、柴胡加竜骨牡蛎湯がこういった症状に効果があるのか
についてですが
それは柴胡加竜骨牡蛎湯に含まれる生薬をみていくと
分かってきます。
ということで次回は、
柴胡加竜骨牡蛎湯の生薬に着目して解説していきますね!
では今回はこの辺で。
なお、このメルマガは
漢方薬をご自身の判断で飲むことを勧めるものではありません。
漢方薬は体質に合ったものを服用することが大切です。
服用に際しては
お近くの漢方薬局などに相談されて下さいね。
また、当院では、漢方薬をご希望のゲストや
鍼灸治療と組み合わせた方がより効果的と思われるゲストには
提携している漢方薬局から処方してもらうということが可能です。
鍼灸治療と漢方薬どちらも同じ方向性でアプローチできるので
相乗効果を期待できます。
お気軽にご相談下さい(^^)