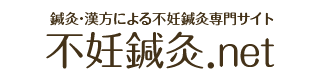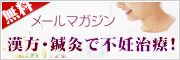夏の味覚-マンゴー(20090730)
2009-07-31 [記事URL]
こんにちは。はりきゅう師の近藤琉水です(^^)
梅雨が長引いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今日取り上げるのは、以前は高級なイメージだったのですが、
最近は国内産もメジャーになり、かなり身近な存在になったマンゴーです。
世界三大美果の一つですね。
スイーツの世界でも人気の高いフルーツです。
原産地はインドからインドシナ半島あたりです。
インド、タイ、フィリピン、台湾、メキシコなどが主な生産国です。
日本でも、沖縄をはじめ、宮崎や鹿児島で栽培されています。
やっぱり南国のフルーツなんですね。
インドではスパイスをかけて生で食べるほか、
ジュースやラッシー(ヨーグルト・ドリンク)、アイスクリームに入れるほか、
チャツネやしょっぱい漬物にだってなってしまいます。
この漬物、最初はギョッとしますが、カレー味で疲れた胃にやさしく、
白いごはんにヨーグルトと一緒に混ぜて食べるとめちゃくちゃ美味しい!
インドではおかゆに梅干的な位置づけでしょうか。
レストランにはない味です。
さて、マンゴーの栄養価です。
ベータ・カロチン、ビタミンC、E、葉酸、カリウム、食物繊維などです。
ベータ・カロチンは体内でビタミンAに変わります。
抗酸化作用や抗ガン作用があります。
とくに肺癌の抑制に効果があるそうですよ。少しずつ摂取するのがよいそうです。
美肌効果も期待できますし、目にもいいでしょう。
そして造血ビタミンの葉酸も多く含まれ、貧血予防によいでしょう。
では漢方的に見ていきましょうか。
性質は涼性、潤、降の働きがあります。
臓腑では肺、胃、腎に入ります。
形からして、腎によさそうな感じがしますね。
五味は甘、酸です。
東洋医学的な効能は、
益胃止嘔、胃の機能を回復し、嘔吐を止めます。
清暑止渇、暑さをさまし、のどの渇きを止めます。
あとは利尿作用です。
体質的に向いているのは熱っぽく、高血圧の方。
身体を冷やすので冷え症の方には向きません。
腎に好いとはいえ、食べすぎはよくありません。
濃厚な味ですから、少量を楽しむのがいいでしょう。
咳や痰が多い方、嘔吐、歯茎の出血のある方にも向いています。
生のトロピカル・フルーツはぜひ夏の季節に食べたいもの。
さまざまなスイーツも楽しみたいですが、
甘いものの食べすぎはよくないですね。
やっぱりマンゴー・プリンやケーキはたまのご馳走にしておきましょう。
マンゴーはウルシ科の植物ですので、かぶれることがあります。
たくさん食べると口のまわりが腫れてきたりしますので、
食べすぎには注意しましょうね。
と言いつつ、私は南国へ行くと市場で山のように買ってきて、
部屋で顔も腕も汁だらけになって貪り食うのが楽しみなんです。
最高にウマイです!!
さて次回は夏の味覚の続きとして、アワビを取り上げてみましょう。
腎にいいんですよ~(^^)
どうぞお楽しみに!
また次回お会いしましょう。