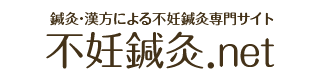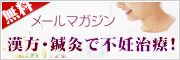いりばくが(20090430)
2009-05-01 [記事URL]
こんにちは。はりきゅう師の近藤琉水です(^^)
季節が逆戻りしたような一週間でしたね。
体調を崩されていませんでしょうか。
今日はまるっきりサプリともいえないけど、漢方生薬ともいいにくいし、
というものを紹介します。分類すると食品に入るのだと思います。
“炒り麦芽”といって、粉末になったものが販売されています。
不妊治療ではけっこうメジャーなので、飲んでいらっしゃる方もあるかもしれませんね。
麦芽といえば、最近ではビールを連想される方のほうが多いかな?
昔は”○ロ”という飲料が有名でしたね。♪強い子のっ ○ロッ!♪
いったいこの正体はなんでしょう?
麦とはいっても大麦ですね。大麦はあまり見たことがないかもしれませんが、
押し麦はあるでしょうか?
丸いままの大麦よりは押し麦の形のほうがよく見かけると思います。
白米に混ぜて炊くと麦ごはんになりますね。
ちょっと前までは貧乏くさいとかなんとかで敬遠されていたのですが、
今は食物繊維もミネラルもいっぱい、ということで見直され、雑穀米を常食
される方が増えました。よいことです(^^)
麦芽というからには、麦の芽、なんですよ。
大麦を発芽させてもやしにして、それを乾燥させたものが麦芽です。
いわば乾燥麦もやしです。
発芽玄米はみなさんご存知だと思いますが、発芽大麦、と考えてもらったらいいでしょう。
それをこんがり炒ったものが”炒り麦芽”なんですね。
だから、麦を買ってきて水につけて発芽させ、それを干してフライパンで空炒りしたら
自分でつくれます。
それを煎じて飲んだら同じなんですが、今では粉末になって個包装された
便利なものが市販されています。
もともと大麦は消化を助ける働きが強く、胃腸のお薬です。
食べすぎて消化不良をおこしたときなど、大麦飯を炊いて食べるといいんですよ。
小麦粉でできたパンや麺類などよりずっといいですね。
ただし、胃腸が弱い方には向きませんので、無理して食べないようにしてください。
漢方的には、
清熱消渇(せいねつしょうかつ)、身体にこもった余分な熱をさまし、
糖尿病に効きます。
益気調中(えっきちょうちゅう)、元気を高めて胃腸の機能を回復します。
寛腸消積(かんちょうしょうせき)、整腸して食滞(食べ物の滞り)を解消します。
などといった働きがあります。
ではその大麦の麦芽となると、同様に消化促進や整腸作用があります。
また、生だと母乳の出をよくし、炒ったものだと離乳に役立つ、とされています。
炒り麦芽は昔から断乳の際に利用されてきました。
母乳の出はプロラクチンというホルモンが深くかかわっていますので、
現在では「高プロラクチン血症」と診断された方が飲むとよいと解釈されています。
このホルモンが高値になると、基礎体温がガタガタになり、着床しにくい状態になります。
授乳中は次の子どもを妊娠しにくいのはこのホルモンの働きによります。
早く断乳して次の妊娠に備えるために古くから炒り麦芽が利用されてきました。
つまり、妊娠しやすくなるというわけですね。
というわけで、高プロラクチン血症で不妊となっている場合に、
この炒り麦芽が利用されるのです。
基礎体温(とくに高温期)がガタガタの方や、低温期から高温期への移行が
スムーズではなく、徐々にしか上がらない方、月経前に胸のハリがきつくなる
といった症状がある方に向いているでしょう。
テルロンなどの高プロラクチン血症治療薬で副作用が出た方も安心して服用できます。
漢方薬でも「麦芽」として古くから伝わるものですし、
一度試してみてもいいのではないでしょうか?
さて次回は中華料理でおなじみの緑の野菜です。
青梗菜、どうぞお楽しみに!
また次回お会いしましょう。