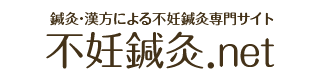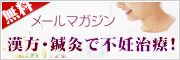涼を楽しむ(20100826)
2010-08-26 [記事URL]
こんにちは! 残暑が続きますが、ここを上手く養生しましょう!
そうすると秋冬の心と身体の状態が良くなりますよ~♪
今回の担当は、はりきゅう師 川上 秀人 です!
連日の猛暑で、みなさんのなかには調子を崩されている方、
上手く過ごされている方、それぞれいらっしゃることと思います。
不調子の方はもちろんのこと、体調はよいけれども暑さに気持ちがまいって
しまった方も結構いらっしゃるのではないでしょうか?
これまでのメルマガでもご案内してきましたように、東洋医学では心と身体は
一つととらえています。
ですから妊娠力を上げるためにはこの暑さのストレスに上手く対処することも
大切になってきます。
ではどうやって対処しましょう?
鍼灸の太古の書物には、季節にあわせて養生をすることの大切さがしっかりと
記されています。
それを踏まえて考えると、自然と一体となって暮らした昔の日本人の知恵が
浮かんできます。
ここはひとつ、昔ながらの”涼をとる”暮らしの知恵を生活に取り入れてみませんか?
なんといっても”風情”があるので気持ちの部分でほっと一息させてくれます。
もちろん熱中症になってはいけないので、クーラーとうまく付き合うことは必要です。
ただ、熱帯夜が続いたりするなか、朝晩いくらか過ごしやすい日も少しずつ
出てきましたので、そんな時に取り入れるのがお薦めです。
手軽な涼のとり方が二つありますのでご紹介します♪
一つ目は打ち水。
私が学生の頃まで(15年以上前の話です)は、実家のご近所さんはみんな
打ち水をしていました。
今ではそんな光景はあまり見なくなったような気がします。
この打ち水、日中はまだ猛暑ですから焼け石に水ですが、朝晩は気持ちいいですよ♪
特に夜はお薦めです。
やり方ですが、だいたいで構いませんので気楽に楽しみながらやってくださいね。
まず、外からご自宅に風が入ってくるところを見つけます。
その風の入り口のすぐ外、玄関やベランダ、窓の前だったりすると思いますが、
そこにお水をまいてあげます。
お水をまく方法は自由です。
さらに”風情”を楽しむためにひしゃくを用意して水をまくのもいいですよね!
これだけです!
やってみると、思いのほか涼しい風が入ってきますよ♪
夜になってから一回、寝る前に一回するとほど良い感じです。
そして二つ目が風鈴。
打ち水の涼しい風の通り道にぜひ吊るしてみてください。
ガラスのもの、鉄のもの、材質によって音色が違いますし、形によっても
音色は変わります。
そして風のリズムが風鈴の音色を何とも言えない独特のものにしてくれます。
不思議なもので、風鈴の音色はほんとに涼やかな気持ちにしてくれます♪
お持ちの方で長らくお使いでない方はぜひ復活させてあげてください。
お持ちでない方はぜひ手に入れて使ってみてください。
お気に入りになりそうなのはどれかな~と選ぶ時も楽しいですよ~。
打ち水と風鈴で”風情”を楽しみながら”涼をとる”。
日本には、四季それぞれに応じた昔ながらの自然との付き合い方が
今に伝わっています。
自然には厳しい側面もたくさんありますが、それらを楽しみながら過ごす
昔の人たちの知恵がそこにはあります。
だから”風情”があるのだと私は思います。
そんな生活の知恵も快適家電がどんどん出てきて忘れてしまいがちです。
身体のためだけではなく”心も豊か”にするために、今に伝わる昔ながらの
“風情ある生活”を少し取りいれてみませんか?
では次回は近藤 琉水先生が担当です。お楽しみに!