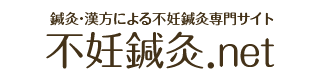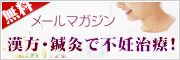【季節の養生法】秋の妊活でしたいこと(20140823)
2014-08-23 [記事URL]
こんにちは。はりきゅう師の池田由芽です(^^)
暦の上ではもう秋になりました。
でも、残暑が厳しく日中の暑さの中、
出かける気にはまだなりません(*_*)
まだ日中は熱中症などが十分起こる暑さです。
油断せず、適度に水分補給をして
早く寝たり、規則正しい生活をして予防していきましょうね!
それでも、朝晩はだいぶ涼しくなってきています。
夜には、虫の鳴き声も聞こえるようになりました♪
この間は駅の中にさまよい込んだトンボを発見しましたよ!
さらに、秋の食材もちらほら出始めています(^^)
食欲の秋、
読書の秋、
運動の秋、
実りの秋
どれをとってもわくわくすることばかりも秋です(゚▽゚)
今年の秋は何に力を入れていきますか?
各地へお出かけするにもいい気候ですよね(^_^)
最近では秋は短くなりましたが、
それでも機会を見つけて情緒溢れる秋を堪能したいですね!
今年も京都の紅葉を観に出かけたいな~
と今から心が躍ります♪
これだけ秋秋、言っていたら、
少し気持ちが涼しくなってきました。
みなさんも夏の暑さにバテそうになったら、
秋のことを想像するのをおすすめしますよ(・∀・)
では、本題に入りまして。
今日は秋の妊活についてのお話です。
せっかく妊活するなら
季節に合った生活を心がけて
自然から生命エネルギーを受け
生命力、そして妊娠力を高めていきたいですよね!?
そう思うからこそ、
このメルマガを読んでくださっているのだと思います。
いつも読んでくださって、ありがとうございます。
1年の中にはそれぞれ季節があって、
季節ごとに違った特徴があります。
春は誕生の季節です。
動物は冬眠を終え、植物もどんどん芽を出します。
夏は成長の季節です。
春に芽吹いた植物たちはみるみる繁り、
森も緑がいっぱいでにぎやかになります♪
秋は収斂(しゅうれん)の季節です。
収斂は”ちぢこまる”という意味です。
この時期に旬のお魚などは身が引きしまっていて
美味しいですよね。
これまで咲いていた花も身を結び、
生命力を種の中に納めるときです。
冬は閉蔵の季節です。
外をとじてもぐりこませる時期です。
冬眠の時期ですね!
ヒトにも、この生命活動の流れがあって
それに合った生活を心がけていると、
元気に過ごすことができ、妊娠力もアップします。
それでは、さっそく秋の養生について
お話していきますね!
秋と言ってもまだまだ夏の名残が残ります。
秋になるとあれもこれもと活動的になり過ぎず、
運動をしても適度な程度が秋にぴったりのペースです。
汗をかいたら、すぐにふいて
身体の陽気を逃がさないようにしましょうね。
陽気を逃がすと
肺が弱って風邪を引きやすくなったり、
冬に下痢をしやすくなったりしますよ。
そうなると、妊娠力にも影響してしまうので要注意です!
また、秋の空気は乾燥してくるので
鼻やのどの粘膜が弱りやすいです。
なので、風邪やさらに鼻炎や喘息になりやすくなります。
手洗い・うがいをしっかりして、
こまめに服装を調整して、体調管理には力を入れていきましょう。
風邪予防としては首の後ろから
肩にかけての部分を冷やさないことも大切なので
タートルネックを着るようにするのも
おすすめですよ。
そして、秋は陰の気が始まる季節でもあります。
メンタル面でもにも憂いや悲しみの感情が湧きやすくなります。
そんなときは「喜ぶ」ことが1番です!
友達とランチに行ったり、
好きな映画を観たり、
音楽を聴いたり、
なんでもけっこうです。
ちょっと気持ちが疲れたら、
自分へのご褒美に何か楽しいことを見つけましょう♪
そして、食養生ですが、
秋に旬のものを今からぼちぼち食べましょう。
季節に順応するために、
小松菜、白菜、チンゲンサイ、タマネギ、
ニラ、ネギ、大根、銀杏、秋刀魚など秋の食材を
食べるといいですよ。
秋と言えば、まいたけ、しめじ、椎茸などのキノコたちも
外せませんよね。
なかでも、松茸は個人的に大好物です!
あの香りがたまりません(^_^*)
ところで、「松茸」の正しい呼び方は
「まったけ」ではなく、「まつたけ」って
ご存知でしたか?
ちょっとウンチクでした(^-^)
あと、最後にもう1つ。
秋は鶏とともに早寝早起きをするといいと
言われています。
これは秋だけでなく、
1年中、続けておきたいことですが、
ホルモンバランスも整えるためにも
できるだけ、早寝早起きして、
規則正しいリズムでいきましょう!
それでは、今回はこのへんで(^^)
次回は万木祥太郎先生の担当です(^o^)お楽しみに!